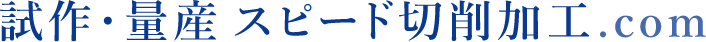薄物フランジの厚み精度を安定させるには
薄物フランジの加工では、わずか数ミクロンの歪みや反りが製品の不良や後工程での組み付け不具合を引き起こします。特に、チャック圧による変形や素材内部の残留応力が原因となる厚みのバラつきは、設計寸法を守るうえで大きな課題です。
本記事では、NC旋盤による薄物フランジ加工で厚み精度を安定させるための基本的な5つの加工テクニックと、材質別の対策ポイントをご紹介します。
厚み精度を安定させるための基本的な5つの加工テクニック
1.油圧を最小にして仕上げる
薄物フランジの厚み精度を乱す大きな要因は、チャックによる締め付け歪みです。仕上げ加工時はNC旋盤のチャック圧(油圧)をできる限り下げ、ワークへの負荷を最小限に抑えます。限界まで油圧を下げても歪みが発生する場合は、手締めのスクロールチャックを併用し、把持力をさらに弱めることで、仕上げ寸法の安定性が向上します。特に内径仕上げでは残留応力による変形を抑えやすくなります。
2.仕上げ加工前に歪みを解放する
荒加工後にチャックを一度開閉し、素材内部に残る応力を解放してから仕上げ加工を行うことで、厚みのバラつきを防止できます。この工程を挟むことで、仕上げ時に発生しやすい「反り」や「面のうねり」を抑制でき、より安定した寸法精度が得られます。
3.入れ子(インサート)を使用する
仕上げ面を直接チャックで掴むと変形が起こりやすいため、内径にぴったり合う入れ子(インサート)を挿入して把持します。入れ子を公差に合わせて設計・製作することで、ワークを均一に支えられるため、歪みを抑えつつ加工精度が向上します。
4.面板・治具を活用する
径方向からのクランプ力をかけずに加工するためには、面板にボルトでワークを固定する方法が効果的です。ロット数が多い場合は、芯出し不要の専用治具を製作することで、作業効率を高めつつ厚み精度を維持できます。
5.幅広・扇形の生爪(チャック)を使用する
ワークを点ではなく面で把持する幅広・扇形の生爪を使用すると、チャック圧を分散させて歪みを防止できます。治具を製作する必要がなく、効率的かつ安定した品質を実現できるため、量産向けの加工に適しています。
材質別の厚み精度対策
ステンレス系フランジの場合
ステンレス鋼(SUS)は硬さと粘りを併せ持つため切削抵抗が大きく、加工中の熱による変形や残留応力が発生しやすい素材です。厚み精度を確保するためには以下の対策が有効です。
・低送り・低切込みで仕上げる:切削熱の発生を抑え、変形を最小限にする。
・ミストまたは高圧クーラントの活用:局所的な熱膨張を防ぎ、加工中の歪みを抑制する。
・荒加工後の応力除去焼鈍(ストレスリリーフ):最終仕上げ時に寸法の安定を確保する。
これらの対策を組み合わせることで、仕上げ面の変形を最小化し、厚み精度のバラつきを防ぐことができます。
アルミ系フランジの場合
アルミは柔らかく熱伝導率が高いため、加工熱がワーク全体に広がりやすく、バリや変形が発生しやすい素材です。対策としては次のような方法が効果的です。
・高回転・低送りでの切削:切削面を滑らかにし、熱影響を減らすことで変形を防止。
・ポリッシュ仕上げの専用バイトを使用:刃先摩擦を減らし、バリの発生を抑える。
・真空チャックまたは治具による固定:クランプ圧をかけずに把持し、歪みを防ぐ。
・最終仕上げをワンチャックで完了:再クランプによる寸法ズレを防ぎ、精度を安定させる。
アルミ加工では「熱とクランプ圧のコントロール」が厚み精度確保の鍵となります。
まとめ
薄物フランジの厚み精度を安定させるためには、「クランプ圧の最適化」「残留応力のコントロール」「材質特性に合わせた切削条件」が不可欠です。治具やチャックの工夫はもちろん、荒加工後の歪み解放やクーラントの活用など、ひとつひとつの対策が最終的な寸法精度に直結します。
これらのノウハウを活用すれば、量産でも安定した品質と高効率の加工が実現できます。当社では、豊富な加工事例と治具設計のノウハウを活かし、お客様の要求仕様に応じた最適な加工方法をご提案しています。
最後までお読みいただきありがとうございました!